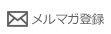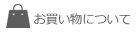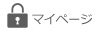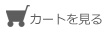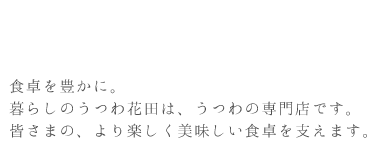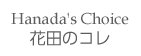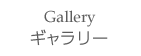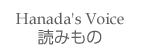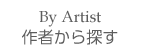父親とスピーカー作り
花田:モノ作りに関わるようになったきっかけは、どのようなものだったのですか。(以下花田-)
鈴木:モノ作り自体は、父親の影響です。父親の仕事は大企業での人事だったのですが、趣味が日曜大工、特にスピーカー作りでした。
それを見たり、一緒にやったりしているうちに、将来はモノづくりを・・・と漠然と思っていました。
-:楽しい経験だったのですね。できたスピーカーでお父様と一緒に音楽を聴く・・・のですか?
鈴木:好きな音楽が違って、当時僕は松田聖子なんかを聞いていました(笑)。
でも、最近、父の趣味と似通ってきましたね。
ジャズとかクラシックとか・・・年を重ねるごとに、当時別に好きでなかったものも聞くようになりました。

自動車から木工へ
-:木工はどちらで学ばれたのですか。
鈴木:大学院(機械工学科)を卒業後、3年間いた自動車メーカーの本田技研を退職後、長野県上松技術専門校で学びました。
-:会社はいかがでしたか。
鈴木:自分で考えて図面を書いて、実際作ったり・・・それは楽しかったです。
ただ、自分は大きい組織で働くのに向いていないとも思いました。
大きな会社にいますと、根回しや調整が非常に大事と言いますか・・・、実際ものを考えて作るよりも事前調整のための資料作りや打合せのボリュームが大きくて、自分のイメージとは少し違いました。
-:技術専門校はいかがしたか。
鈴木:すごく楽しい。一度勤めた後に通う学校はとても楽しいです。
-:ありがたみが違いますね(笑)。

独立へ
-:訓練校のあとはどうされたのでしょうか。
鈴木:木工の会社に就職しました。東京の会社でしたが、そこの製品を、木曽町のこの場所で、おじいちゃんの職人さんが1人で作っていました。
それを手伝うということで、訓練校の後も木曽に残りました。とても面白かったです。
-:よかったですね。
鈴木:気さくな方でした。同時すでに80才手前で「もう辞めたい」と会社に伝えている状態でした。
-:色々学べそうです。
鈴木:訓練校では、家具の一点ものを作るような感じでしたが、その職人さんからは数を作ることやその考え方を学べました。
時間の考え方も機械の使い方も全然違いました。
「どれだけ早く正確に作ることができるか」が基本になります。

-:スムーズにスタートできましたか。
鈴木:「意外とできるな」とは言われました。
体がでかいから、細かいことが苦手そうに見えるんだと思います(笑)。
2年くらい経った時に、その職人さんが引退し、自分も独立のきっかけになりました。
30才過ぎた頃です。
家具から、食器、カトラリー
-:作家さんとしての活動は、どのような形でスタートしたのですか。
鈴木:オーダーメイド家具中心でスタートしました。
そのうち、家具を作った時に出る端材で作り始めたのが、食器類でした。
お皿、スプーン、フォーク・・・。

-:当時からスタイルは定まっていたのですか。
鈴木:独立した頃、世の中にはシンプルなものが多かった気がしますが、自分は装飾的な部分も持ったものを作りたいと思って始めました。
まず色々な形を作って、そこから「いいな」と思うものを選んで、それをブラッシュアップしていくことを繰り返して、今に至っています。

日々追いかけるもの
-:モノを作る上で大切にしていることはありますか。
鈴木:同じ形を作らない・・・といいますか、最初は、ぴったりと同じものを作ろうとしていました。
同じ形をずっと作っていると、技術は上がりますが、その形自体が良くなる機会を逃しているとも思います。
自分にもし求められているものがあるとしたら、自分で正解の形を決めてしまって、その量産を続けることではなく、いいと思えるものを日々追いかけていくことだろうと思うので。
-:そういった変化は、現役作家さんの仕事を追いかける楽しみでもあります。

鈴木:あと、普段はあまりモノ作りについて言語化しないようにもしています。
言葉や数字にしてしまうと、それにとらわれてしまうこともあるので。
勤めていた時のように、組織でモノを作っている時には言語化、数値化は必要ですが、自分だけで完結できるのなら、敢えてしない方がいいかなと。
何かをいいと思った時にその理由は考えますけど、決めつけずに、常に変えていくことを念頭に・・・今は「変化」がテーマです。
-:ずっと数字を追いかけてきたからこそ、追わないことの意味も分かるわけです。
鈴木:数字はわかりやすいですが、それ以上に大事なのが、その数字の根拠です。理系だからこその視点かもしれませんが。
-:カトラリー作りの際は、図面などは用意するのですか。
鈴木:書くものもあります。
特に先端などは、大まかなに書いて、型を作ることもしますが、やはりこれも、それにとらわれ過ぎず、作りながら、もっといいと思う形が出てくれば、それを優先していこうと思っています。
木材は個体差も大きいですから、それに合わせた形を優先したいです。
-:カトラリー作りは本当に難しいと思います。
格好いいだけでは使い続けてもらえないし、使えるだけでは手に取ってもらえない。
鈴木:今は道具を作っているので、道具として使えるものを作るようにはしています。
強度であったり使い心地であったり・・・。
色々な要素が及第点を満たしていて、それらがバランスよく成り立てばいいなと思います。

これからのこと
-:学校で機械工学を学び、就職して自動車作りにかかわり、職人さんの下で家の道具類をたくさん作り、そして今は独立して、生活道具を作られています。
鈴木:それぞれ違いますが、モノを作るということはどれも共通しています。
技術や考え方など、それぞれが自分の中で活きています。

-:今後について、何か考えていることはありますか。
鈴木:用途のないものも作ってみたいです。元々、工学系なので、用途のあるものしか作ってきませんでした。ずっとあったその指標を外されると何も作れないかも・・・とも考えますが、挑戦してみたいです。家具などの大きいものもまた作りたいと思っています。
-:楽しみにしています。展示会もよろしくお願いします。
鈴木:現段階でのベストのものを作って、ご覧いただけるようにします。

▼鈴木亜以×鈴木潤吾×松本優樹 三人展のご案内はこちらから ▼