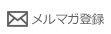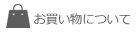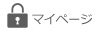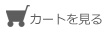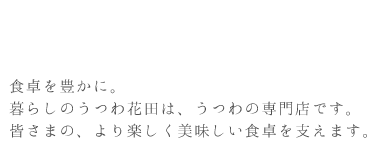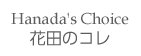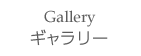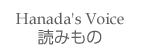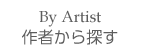責任感と喜び
花田:小林さんはご実家が窯元さんでした。その影響で今のお仕事を選ばれたのでしょうか。(以下花田-)
小林:きっかけは「長男として継がねば」という責任感でした。
ただ続けている理由は別です。
子どもの頃、家にあった素焼きの余りの小皿にポケモンを描いて友達にあげたら、とても喜ばれたんです。
自分の作ったもので人が喜ぶという、そのシンプルな嬉しさが今も支えになっています。

-:ご実家で、焼き物屋さんの仕事ぶりをお父さんの姿に見ていたわけです。
小林:工場(こうば)は遊び場でしたし、生活の一部になっていました。
僕らがチョロチョロするから、素地を渡されて「これに絵を描いて遊んでいなさい」みたいな。
記憶にないのですが、窯の還元をかけるドラフトという部分に石を詰めて、ひと窯分を全部ダメにしたこともあったらしいです。
親によると、正座させられて大分怒られていたらしいですけど…。
-: それは、大変でした(笑)。

秦さんとの出会い
-:自然と進路は焼き物に考えられたのですか。
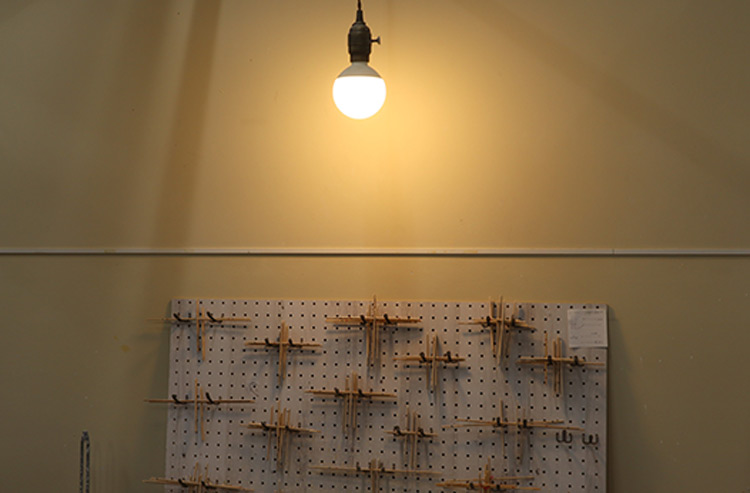
小林:進学した有田の高校では、窯業科ではなくデザイン科を選びました。
当時はインテリア、特に照明を使った空間デザインに興味がありました。
で、大学で初めて、ロクロに触れたんです。
実家は絵付け専門でしたので。
その時「好き」というより「向いているかも」と感じました。
そのあたり、ですかね。
ただ、すぐ戻る気はなく、ある方の紹介もあって九谷青窯に出会いました。
成形から絵付けまで一貫してやると聞き、いきなり青窯に入社するのは不安でしたが、九谷青窯の秦さん(故人、九谷青窯主宰)が研修所を紹介してくれました。
研修所で2年間、死に物狂いで学びつつ、青窯にも顔を出していました。
別に用事があったわけじゃないんですけど。

-:研修所に行っている間に、忘れられても困りますものね。
小林:そうなんです。
気持ち変わられても困りますし(笑)。
品物を見てもらったり、ろくろを教えてもらったりしました。
秦さんが、目の前でひいてくれて「こうやってひくんだよ」って。
-:それは貴重ですね。
小林:はい。
あとから、皆に「珍しいよ、秦さんがロクロひくのって」って結構言われました。
-:どの様な感じでしたか。
小林:当時はまだ比較対象がなかったので「うまいな」くらいでしたけど、今思うと、なんて言うか…、全く力の入ってない、自然に形が出来上がるというか。
なんですかね、あの感じ。
ひゅっと出来上がるんですよね、形が。

いきなり1000枚
-:研修所で2年過ごされ、晴れて青窯に・・・。
小林:いや1回、断られるんですよ。
あれだけ行っていたのに…。
「お前は真面目すぎるからダメだ」って…。
「もっと遊べ」ということを言う人だったから、分かるんですけどね。
「いやいやいやいや…」って、思いました(笑)。
そのあと、一カ月位空けて「やっぱりここしかないんです」って行ったら、「うん、わかった。
じゃあ、来いよ」って感じで。
-:(笑)。よかったですね。最初はいかがでしたか。
小林:研修所にいる時から、秦さんに「ロクロだけはしっかり、やっておけ」と言われていたので、誰よりもろくろは回して、研修所では圧倒的だったと思います。
実際そこそこひけていたんです。
だからなのか2日目に「これ、1000枚ひいておいて」って言われて。
4.5寸くらいの皿でした。
-:いきなり・・・。
小林:元々、青窯は数を作るところだと聞いていたので「そんなものかな」と思っていたのですが、後から皆にその話をしたら、「そんなこと、やっていたの」って…。

-:周りが気づいていないのも青窯っぽくて、いいですね(笑)。
小林:「めっちゃ、ひいてんな」という感じはあったらしいのですが「1000枚もやっていたんだ」みたいな(笑)。
まあ、みんなそれぞれ忙しいですから。
先輩たちのロクロ
-:ロクロの鍛練になったのですね。
小林:研修所では自信がありましたが、青窯で一番ロクロが上手な二人が両隣で、現場で働く方々との差を痛感しました。
スピード、正確さ、体力、すべてが違い、僕は必死で形にしているのに、彼らは軽くひいて次々と台車を埋めていきます。
彼らの仕事を観察し、実際に器を触って、どこをどれだけ残しているのか見てみたり、不良品を割って断面を確認したりしていました。

-:ご自身のものとの違いは大きかったですか。
小林:見た目は、そこまで変わりません。
違いは、土の締め方なんですよね。
ろくろを引くときに、しっかり締めているから、焼いた時に綺麗に上がるんです。
-:先輩に倣いつつ、上達されていかれたのですね。
小林:真似しました。
青窯はコテを使わないんですけど、ここをコテ代わりに使って土をギューっと締めているんですよね。
あと水の量。
量が多いと表面が滑ってひきやすい反面、摩擦が減るので、締まりが悪くなります。
だから、余計な水を使わずにひくというか。

-:最初に1000枚ひいたら、のちのハードルは下がりますね。
小林:「1日100枚くらいはひけないと仕事にならない」とよく言われていたのですが、1日200枚ひける人が100枚ひくのと、1日100枚ひける人が100枚ひくのでは、上がりが違うと思います。
その部分を体験させるための1000枚だったのかなとも思います。
-:他にも秦さんからも色々声を掛けられたと思います。
小林:「自分がこの皿をどう使いたいか、この料理を食べる時にどういう皿がいいのかイメージしながら物を作れよ、漠然と物を作るなよ」という言葉が今1番残っています。
それと、秦さんよく言っていたのが「惚れ込め」でした。
時代でもいいし、産地でもいいし、陶工でもいい。
何でもいいんですけど、何かに惚れ込めって。

-:そして、独立です。
小林:色々経て、この石川県で作家としてやっていくことにしました。

大事なこと
-:器を作る上で、大事にされていることは何ですか。
小林:食器のままで、食器として完成させず、料理を盛って、初めて完成するよう意識しています。
それと、自分の思いを詰め込みすぎないようにしています。
入れ込み過ぎると使いづらくなるかなって。
僕は自分が作った食器が、選んでくれた人の食卓で役割を果たしていれば、そこに僕の存在は必要ない、誰が作ったかは、どうでもいいなと思っています。
-:新作などはどのように生まれてくるのでしょうか。
小林:とにかく1回形にしてみて、まず自分で使ってみる。
使ってみると、意外な発見もありますし、アイデアも生まれてきます。
最近は、しのぎに凝っています。

感謝のバトン
-:これから取り組んでいきたいことは、ありますか。
小林:青窯の環境は自分にとって本当にありがたいものでした。
そのような場を自分でも作りたいと思っています。
研修所では優れた人が環境に恵まれずに焼き物をやめていく姿も見てきました。
幸い実家にスペースがあるので、そういった人たちと青窯のような場をつくることを、漠然とですが、目標にしています。
-:同様の場を作るとなると、設備環境も求められますが、あの場を体感していることも大切ではないでしょうか。
小林:自分の目で見て、耳で聞いて、自分の身体で経験したものですよね。
ああいう環境って、表面的なことをなぞっても、意味ないと思います。
青窯は精神的な部分をしっかり持っていたからこそ、青窯出身の人たちが、たくさん活躍されているんだろうなと思います。
-:夢が広がりますね。展示会、よろしくお願いします。
小林:食卓をイメージしながら手に取っていただけたら、嬉しいです。
▼小林巧征×中川紀夫×武曽健一 三人展のご案内はこちらから ▼