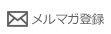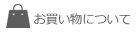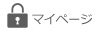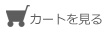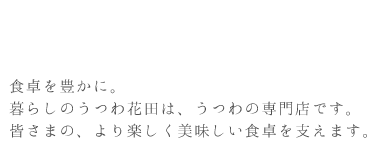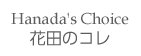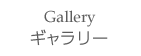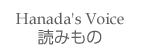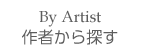手仕事に関わりたい
花田:うつわ作りに取り組むようになった経緯をお聞かせください。(以下花田-)
武曽:最初は、大阪でインターネット関連の仕事をしていましたが、20代後半くらいに郷里の福井に戻ってきたタイミングで、手仕事に関わることを考え、福井県内の工芸の産地を回りました。
漆、刃物、和紙、焼き物…。
最終的には和紙と焼き物に絞りました。
-:元々、手仕事に興味をお持ちだったのですか。
武曽:昔から、絵を描くことや美術の授業が好きだったり、音楽をやっていたり…。
何かを自分の手で生み出すようなことが好きだったのだと思います。

出会い
-:和紙と陶芸が最後に残ったのですね。
武曽:和紙は以前にもハマっている時があって、色々和紙の産地を見て回ったこともありました。
焼き物は、近所に「創作の森」という場所があって、そこを見学していたら、陶芸家の教室に勧誘されたんです。
そのうち、その陶芸家さんとも仲良くなって、その方の自宅にも遊びに行くようになり、その暮らしの面白さに魅かれました。
その人とは音楽の趣味も合いました。
一緒にライブ行ったり…。
ブラック、ラテン、ジャズ・・・僕も色々聞くんですけど、その人も色々好きな人でした。
その人がそうだったのかもしれませんが、暮らし方がとても大らかで自由だったんです。
そのうち、薪窯を焚く手伝いをさせてもらったり、レゲエ聞きながら土練りしたり…。

-: 好きな音楽聞きながらだと、楽しいでしょうし、伝統工芸という割には、そういう音楽を聞きながら、というのにも何か魅力を感じますね。
武曽:そうです。
特にその人は越前焼がメインだったのですが、そういう人が、そういうノリで仕事をしているのが、いいなって。
なんか腑に落ちたというか。
その人に、越前の窯業指導所について教えてもらい、そこに研修生として入ることにしました。
-:そこでは、どういった指導を受けるのですか。
武曽:基本的にロクロだけです。
あとちょっと釉掛けとか…。
結構、自由にはできたのですが、一応課題があって、湯飲みが終わったら、次お皿、それが終わったら鶴首みたいな感じで、ペースが早い人はどんどん進めますが、1年しかないので、遅い人は途中で終わってしまう、みたいな…。
あっという間でした。
その1年のあとは「もう独立して、やっていくんだ」って、当時は、なんか変なやる気というか、根拠のない何かがあって。
自信があるわけでもないのに(笑)。
さらに、研修生の終わりぐらいの時に、ちょうど焼き物をやめるという人に「窯とかロクロとか、一式売るよ」って声を掛けられて、まだ研修生のくせに「もう、買ってしまうかな」と思って、買っちゃったんですよ。
まだ習っているだけなのに…。

武曽:で、そこで、いわゆる独立をしました。
「やった。独立だ」って一瞬喜んだんですけど、当然ながら、全然、仕事ないんですよね。
自分の釉薬すらないから、まずは釉薬を作ることにしたのですが、そうしたら譲ってもらった窯が大きくて、釉薬のテストピース作ろうにも、一向に窯が埋まらない。
で、結局半年仕事がなくて、自分の釉薬も作れずじまい。
「これはやばい、何かしないとまずいな」って。
で「一旦諦めるか」と考え直していた時に、窯元さんから仕事のお誘いを受けました。
-:いかがでしたか。
武曽:いやあ、行って良かったです。
作ることはもちろんですけど、販売することの重要性を学びました。

作りたいもの、好きなもの
-:そしてついに、リアル独立ですね。作風は現在のような感じでしたか。

武曽:元々、李朝の焼き物が好きでしたし、地元の赤土でずっと練習していたり、まわりに粉引の作家さんも多かったりしたので、自然と粉引を作るようになりました。
福井の雪をイメージもしています。
-:地元の風土に愛着をお持ちなのですね。
武曽:黄色は大地で、グレーは福井の曇り空。
「曇り空」って、テーマとしては、あれかもしれませんけど(笑)。
-:ブルーは青空ですか?
武曽:海です。

-:絞手の仕事も魅力的です。
武曽:自分の好きな安南の焼き物をアレンジしました。

-:ご自宅には古いものが色々と置いてあります。
武曽:骨董に限らず、古くから使われている道具が好きです。
こういう引き出しだったり、杉の板だったり…。
イスラム陶器やイランの陶器の文様も好きです。

自分に正直に
-:うつわを作る上で、大切にされていることを教えていただけますか。
武曽:「オリジナルであること」です。
自分にしかできないようなものを作っていきたいですし、なんというか、自分には正直でいたいです。
使うための食器作りではありますが、それにプラスして、遊び心や、いたずら心を入れた「これ、何に使うの」みたいなものも、作っていきたいなと思っています。

-:例えば、どのようなものですか。
武曽:僕、小さいものがすごい好きなんです。
小さいものにギュっと凝縮されてる感覚が好きなんですよ。
「これ、何入れるの」っていうくらい、小さいもの。

-:色々あって楽しいですね。まあ、人間、したいことが1つにまとまるわけでもありませんし。
武曽:そうなんです。
同じことをずっとやっていると、全く違うことをやってみたくもなります。
それと、手に取った時の重さも気にしています。
特に手に取って使う湯呑みやマグは「見た目より、ちょっと軽め」を意識しています。
あとは、できるだけ最初の熱量を維持しながら取り組むことです。
焼き物は、作り始めてから焼き上がるまでに1ヶ月くらいかかってしまうこともあるので、作り始めのモチベーションを失わずに、集中力が途切れないよう、音楽聞いたり、畑いじったり、植物散歩したり…で、結構その気分転換の時間の方が長くなることもあるんですけど(笑)。

-:同じものを作り続けていく場合にも求められそうです。
武曽: 例えば、昔から作っている印花だと、どうしても作業化しやすいというか…。
マグカップも30個、50個ってなってくると、こなしに入ってしまいがちです。
そういう部分はモノにも出てしまうと思うので、熱量の維持のためにも、やはり新鮮な気持ちになる時間は大切です。

これからも続けていきたい
-:今後、取り組んでいきたいことはありますか。
武曽:元々の夢が、この仕事を続けることだったので、かないつつあるのですが、それに加えて、やはり自分にしか作れないものを作り続けていたいという思いはあります。
釉薬も色々テストしていますので、新しいものも作っていきたいです。
-:楽しみです。ありがとうございました。
▼小林巧征×中川紀夫×武曽健一 三人展のご案内はこちらから ▼